お知らせ:
2022(令和4)年3月、的射場敬一先生が退職されたことに伴い、国士舘大学政経学部 的射場ゼミの活動は終了しました。
(2022年03月14日 政経学部・的射場敬一教授の最終講義が行われました)
(紹介記事:国士舘新聞第528号(2022年4月25日発行)5頁抜粋)
また、同年6月、的射場敬一先生に名誉教授の称号が贈られました。
(2022年06月15日 名誉教授記授与式を挙行しました)
(紹介記事:国士舘新聞第529号(2022年7月25日発行)2頁抜粋)
ゼミOB会について:
5月第3土曜日及び11月第3土曜日に開催しています。ゼミ卒業生の皆様の参加をお待ちしています。
(開催の有無やその詳細は、主にFacebookでお知らせしていますので御確認ください。)
 |
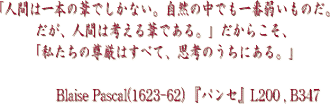 |
「大学で学ぶ」ということには、二つの側面がある。過去の遺産の継承と創造である。それぞれは講義とゼミに対応している。講義の役割は過去の遺産の伝達である。それはある面で、教師からの一方的な知の伝達にならざるをえない。これに対して、知の創造の役割を果たすのがゼミ活動である。そこでは、教師の役割は学生の創造活動の産婆でしかない。教え込むのではなく、ただ、我々の創造の苦しみに立ち合い、援助する存在である。問答法によって、知の創造を助けんとするのである。
ゼミはまた、学生の共同研究の場でもある。お互いに切磋琢磨し、自己を磨いていく場所である。報告、討論、相互批判を通して、自己の考えを論文としてまとめあげていくのが、ゼミ活動である。
このゼミでは、あえて共通テーマを設定せず、自分にとって一番切実なテーマ、関心のあるテーマを、深く掘り下げること、そしてそれを皆にわかる言葉で語ること、これを基本に活動している。それぞれの論文は各自の責任のもとに作成されたものではあるが、しかし、そこには他のゼミ生による協力が反映されている。幾度も幾度も議論を重ね、書き直し、それが最終的な論文となっている。テーマは様々だが、活発な討論は、様々なテーマを孤立分散させず、共鳴させている。
主体的に考えること。徹底的に考え抜くこと。他人の批判を受け入れ、自己解体と再創造を繰り返すこと。そしてそれを自分の言葉で表現すること。このような活動の集約としてこの論文集がある。この「パンセ」(思索)は、我々が「考える葦」たらんとした成果である。
(的射場ゼミ論文集『PENSÉE(パンセ)』巻頭言から)


